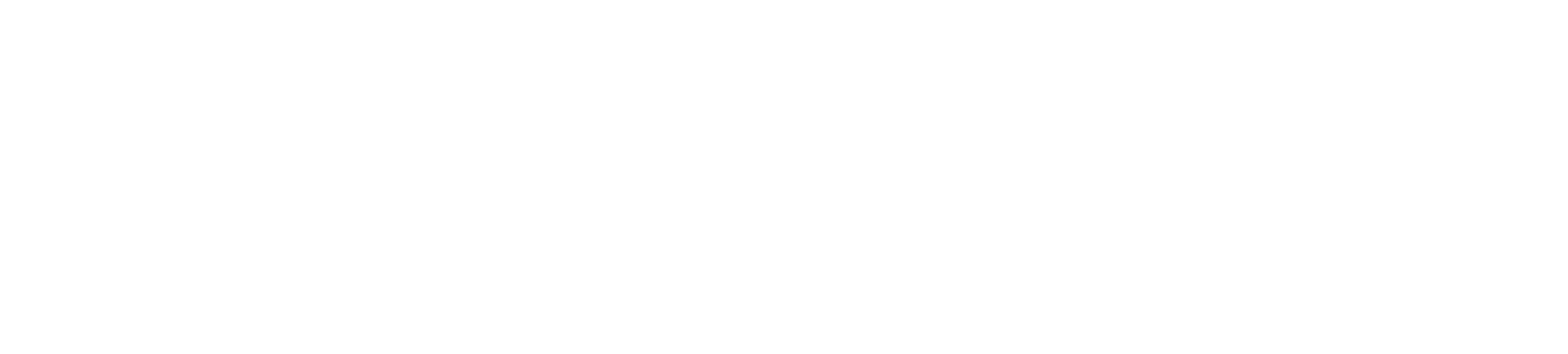それは、高音質を実現するための、「最も簡単」な方法で、「誰でも再現可能な方法」だからです。
シンプルに言い換えます。
音量を上げれば高音質が実現できます。
詳しく解説していきます。
はじめに
大音量と聞くと、
「外に向けた音」
「自ら音を歪ませる行為」
そう思われている方も多いのではないでしょうか。
そうですよね。私も以前はそうでした。
街中で「ドンドン鳴らして走る車」に対する印象は、決して良くありません。だからこそ、「迷惑に思われるのでは」という葛藤がありました。
一方で、音響工学の視点から見ると、大音量こそが高音質を実現する上で不可欠な要素だったりします。
とは言っても…。
「迷惑に思われるかも」という気持ちは変わらない。
そんな方に、この記事では「S/N比」という指標から、なぜ高音質には大音量が必要なのかを解き明かしていきます。
この記事を読めば、大音量に対する抵抗感や「ドンドン鳴らして走る車」に対する印象も変わるかもしれません。
高音質を表す指標のひとつ | S/N比とは何か
音量をあげると高音質が実現できるといっても、そもそも高音質というのはどういうことを言うのでしょうか。
・「高音が綺麗」
・「ボーカルがクリアに聞こえる」
よく聞く言葉です。
しかし、これらはあくまでも主観に過ぎません。
客観的に高音質を表すにはどうすればいいのでしょうか。
もちろんデータです。
客観的に高音質を指す指標、あります。
「S/N比」です。
S/N比 = Signal(信号) と Noise(ノイズ) の比率
S/N比は、「ノイズの大小」という面において、高音質を計る一つの指標で、この比率が大きいほど、ノイズが少ないことを意味し、一般的に高性能(=静かでクリアな音・高音質)とされます。
単位はdB(デシベル)で表されます。
デッキやアンプの仕様には基本表記されており、信号がゼロの時でも発生しているノイズを1とした場合、
その機器が出せる最大の信号が、ノイズに対してどれだけ大きい(離れている)か
という数値になります。
(※なお、機械には必ずノイズが存在します。詳しくは後述)
カーオーディオ機器において、高音質のラインは90dB
ただ、これはデジタル機器において。という前提条件が必要です。
アナログ機器というと、真空管アンプ、A級アンプ、AB級アンプ、レコードプレーヤーのことを指します。
以下の表をご覧ください。
表1: カーオーディオデッキ(ヘッドユニット/DAP)のS/N比
| 機器タイプ | 方式 | S/N比目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アナログレコードプレーヤー | アナログ | 60dB | アナログ方式の代表例 |
| スマートフォン(iPhone等) | デジタル | 90〜100dB | ・機種により異なる ・第三者の測定により16bitのCD規格を超える性能が確認されている。 |
| カーナビ・ディスプレイオーディオ | デジタル | 90〜105dB | ・純正品は90dB前後 ・高級機は100dB超 |
| CDプレーヤー | デジタル | 96dB (理論値) | CD規格の理論上の限界値 |
| デジタルオーディオプレーヤー(DAP) | デジタル | 96〜120dB以上 | ハイエンド機では120dB超も |
| ハイレゾ対応DAP | デジタル | 100〜146dB | 24bit対応機は理論値である146dB |
表2: カーオーディオアンプのS/N比
| アンプタイプ | 方式 | S/N比目安 | メリット | デメリット | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB級 | アナログ | 85dB~110dB以上 | ・自然で音楽的な音色を持つ製品が多い ・長年の実績と信頼性あり | ・D級に比べ効率が低く、発熱やサイズが大きい傾向あり ・同出力のD級より高価になることが多い | ・音質を重視するフルレンジシステム ・伝統的なアナログサウンドを好むユーザー向け |
| A級 | アナログ | (105dB以上) | ・理論上、最も歪みが少なく高音質 ・非常にリニアな増幅 | ・極端に効率が悪く、巨大な発熱とサイズ ・現在カーオーディオ用製品はほぼ皆無 | ・(主にホームオーディオにおける)究極の音質追求 |
| D級(エントリー) | デジタル | 78dB~90dB | ・安価 ・小型・軽量 ・高効率(低消費電力・低発熱) | ・S/N比が比較的低い ・音質面で妥協がある場合が多い | ・純正からのステップアップ ・省スペースでのサブウーファー駆動 |
| D級(ミドル) | デジタル | 90dB~100dB | ・優れた電力効率 ・コンパクトなサイズ ・コストパフォーマンスが高い | ・一部のAB級と比較して音色の好みが分かれることがあると言われている | ・現代のカーオーディオシステムの主流 ・フロントスピーカーからサブウーファーまで幅広く対応 |
| D級(ハイエンド) | デジタル | 100dB~105dB以上 | ・高効率と高音質を両立 ・AB級ハイエンドに匹敵する音響性能 ・コンパクト | ・高価 ・製品数が限られる | ・音質と効率を妥協したくないハイエンドシステム ・省スペースでの高音質 ・大出力の実現 |
| DSP内蔵アンプ | デジタル | 100dB~116dB以上 | ・統合された制御が可能 ・高度な音響補正機能 ・デジタル入力時の高S/N比 ・省スペース | ・設定が複雑 ・アナログ入力時はADCの品質が性能を左右 ・高価になる傾向 | ・車内音響を最適化したい方向け ・単体でシステム全体を駆動・調整できるある意味究極のソリューション |
ということで、カーオーディオでいうと、
現在はD級アンプやデジタルオーディオプレイヤー(DAP、iPhoneもこれ)がメインですので、S/N比が90dB以上であれば「ノイズの大小」という面において高音質と捉えていいでしょう。
とは言え、メーカーの仕様表には、S/N比の表記はあれど、測定方法が明らかにされていない場合が多いです。
そのため、繰り返しにはなりますが、
S/N比は実用域において「静かでクリアな音」の指標ではなく、
その機器での最大出力時の信号が「静かでクリア」かどうかという指標になります。
実は、そのような中でも、実用域でのS/N比をある程度求める方法は存在します。
→ 詳しくはこちら: 実用域でのS/N比測定方法 | メーカー仕様表の真実 (近日公開予定)
ノイズの全くない機器は存在しません
電子回路を持つ機器(アンプやデッキなど、電源を必要とするもの)において、全く信号がないからと言って、ノイズを完全にゼロにすることは物理的に不可能と言われています。
これは主に熱雑音(ジョンソン=ナイキスト・ノイズ)と呼ばれる現象が原因です。
熱雑音(ジョンソン=ナイキスト・ノイズ)とは
回路内の抵抗器などの部品に含まれる電子が、
温度(熱)によって不規則に振動し、
その振動が微弱な電気信号(=ノイズ)として現れます。
このノイズをジョンソン=ナイキスト・ノイズといい、物質が絶対零度(約-273℃)でない限り必ず発生します。
※略してジョンソンノイズという方が一般的です。
S/N比は、機器だけの話ではなく、現実世界でも有効な考え方
ということで、S/N比を、実際の視聴環境に置き換えて表してみます。
- Signal(S) = 音楽再生音
- Noise(N) = 風切り音、ロードノイズ、エンジン音など
高速道路で100km/hを出しているとき、風切り音やロードノイズは大きくなりますよね。
そうすると、音楽は風切り音やロードノイズによって、聞こえにくくなります。
この時、あなたは、音楽の音量を上げるはずです。
実は、これこそがS/N比を上げる行為なのです。
(ピンとこない気持ちはわかります。最後にはわかりますのでご安心を。)
音量を上げるとS/N比が上がる(高音質になる)理由
ここが重要なポイントです。
1.音量を上げる = Signal (S) が上がる
(例:1 → 10)
2.Noise (N) はそのまま
(仮に1なら1のまま。風切音は音量に左右されないため)
3.だから、S/N比が上がる
これまで 1(S)÷1(N) = 1(dB)
音量上げる 10(S)÷1(N) = 10(dB))
つまり
- 音量を上げる = S/N比が上がる
- S/N比が上がる = 高音質になる
だから、音量を上げる=高音質になるというわけです。
音量を上げるに伴い、これまでノイズに埋もれていた細かな描写も聞こえるようになります。
🎵 S/N比の視覚化
周波数特性とノイズフロア
🚗 高速道路での視聴環境(100km/h)
音量のスライドバーを動かすことで、音量と高音質の関係が確認できます。
💡 重要なポイント
音量を上げると…
① 周波数特性グラフ全体が上に持ち上がる
② ノイズフロア(赤い線)はそのまま固定
③ ノイズフロアより上に出た部分が聞こえるようになる
④ これまで埋もれていた低音や高音の細部も聞き取れる!
⚠️ ただし、純正スピーカーでは限界があります
→ 詳しくはこちら: なぜ純正スピーカーでは限界があるのか | 磁気回路とフレーム剛性の真実 (近日公開予定)
まとめ | 高音質には、大音量が必要です
この記事では、「なぜ湯けむりガレージは大音量にこだわるのか」を解説してきました。
- 高音質と大音量は、切っても切れない関係です。
- 音質を決定する本質的な指標の一つは「S/N比(信号と雑音の比率)」です。
- そして、音量を上げることで、S/N比が向上し、高音質になります。
- 大音量でも、音を歪ませず、クリアで豊かな音圧を得ることが可能です。
ただし、大音量を出せば自動的に高音質になるわけではありません。
- 大音量に耐えられる機材
- 大音量に耐えられる施工
この2つが揃って初めて、「大音量×高音質」が実現します。
あなたの車で「大音量×高音質」を実現するには
この記事で、高音質には大音量が必要であること、
そして、歪みのない大音量を実現するには「機材」と「施工」が必要であることが理解いただけたかと思います。
しかし、
「自分の車に必要な機材は?」
「どんな施工が必要なのか?」
「そもそも今の状態で何ができるのか?」
そんな疑問が湧いてきたのではないでしょうか。
本来であれば、それらを解説する記事を用意すべきところですが、あなたの車の環境、予算、求める音質は、一人ひとり異なります。
攻略本(YouTubeなど)には、あなた専用の答えは載っていません。
もし、
- 今の車で実現できる音質の限界を知りたい
- 自分に最適な機材と施工プランを相談したい
- 湯けむりガレージの施工を検討している
そう思われたなら、まずはお問合せください。
あなたの車に、どんな「補助魔法」が必要なのか。
秋田の音響工房で、お待ちしております。